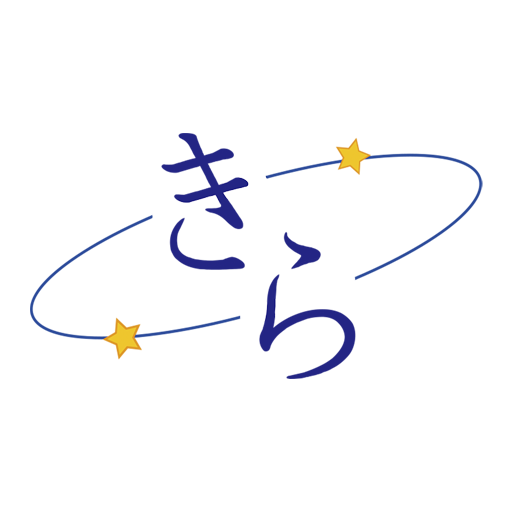気泡六分儀編
六分儀の紹介のところで最近まで大洋航海中の船では使用されていると記しました。衛星航法が主体となるまでは現役だったのです。これは飛行機でも同じです。
飛行機の場合、視野が広い(高いところを飛ぶため)為、航海中の船ほどの精度は必要ありませんでした。また高度によって水平線の見え方(角度)が変わってしまうため水平線を目視しつつ水平(0度)規定するのは現実的ではありません。また雲の上を飛行しているときも水平線を見ることはできません。
それらの事情から水準器と同じ原理の気泡によって水平を規定することとしています。
水準器は1分程度の傾き感度があるので、天測の要件は満たしていると言えましょう。写真の気泡六分儀は戦中に海軍で使用されていたものです。現在、気泡が抜けてしまっているので実際の使用には耐えられませんが、構造的には星を導入し反射するハーフミラーと気泡が同一視野に入るように作られています。そして星を導入するためのダイヤルのようなものがついています。ダイヤルを調整して気泡と対象物を一致させると、その時のメモリが高度となります。
さて海軍で使用されていた気泡六分儀となると、どのような使われ方をしていたのでしょうか。
船上で行われる天測計算は、煩雑さを極めます。熟練者で5分程度は位置測定にかかるでしょう。船の速度ではそれはそれで良しとされますが、飛行機の場合かなり厳しいものがあります。さらに乗員の少ない機では、操縦と天測を行わなければなりません。飛行の安全性の課題も生じます。
それでも、時間に余裕もあり練度もあげられる時代と機なら可能でしょう。
一方で戦時です。搭乗員の訓練も限られた時間で行わなければなりません。
まず前提ですが、天測は自船或いは自機のいる場所の緯度・経度を知るために行われます。星を観測して高度を出し、天測計算を行った結果は、緯度と経度で示され、それを海図や地図に落とし込むのです。
第二次世界大戦中、日本の海軍は発想の転換を図りました。限られたリソースから導かれた逆転の発想です。
任意の時間の星の高さから緯度経度を知るのではなく、ある特定の地点にいたならばこの日、この時刻には特定の星がこの高さに見えているはずだ。っとするのです。
搭乗員は星の高さを測定し、事前に計算された特定の地点の高さと比較します。結果、その地点に行くにはどのように飛行すれば良いかを知ることができるのです。
原理は単純ですが、これは事前に膨大な量の天測計算をしておくことを意味します。
海軍水路部が指導しながら勤労奉仕で参加した女学生たちが実際の計算を行いました。
その計算結果はマル秘とされつつ、「高度方位暦」として刊行されています。
昭和19年から昭和26年まで発行されました。
戦後はその実用性の高さから漁船での使用を想定して発行が行われていたものです。
この高度方位暦からも様々な事を感じることができます。
実はこの高度方位暦は戦中に使われていたことは明らかだったのですが、平成22年に山梨大学の高橋智子准教授より海上保安庁の倉庫にて確認されました。
昭和19年の6月~12月は8箇所(横須賀、父島、南鳥島、ウェーク、サイパン、トラック、パラオ、ラバウル)で計算されています。※毎月刊行されていました。
それが昭和 20 年2月のものでは 11 箇所(横須賀、父島、硫黄島、鹿屋、那覇、高雄、サイパン、トラック、マニラ、ダバオ、モロタイ)と日本周辺に移り、昭和 20 年5月のものでは4箇所(木更津、硫黄島、鹿屋、那覇)となります。
当時、計算を行っていた女学生たちも戦線が本土に近づいてきているという実感があったとの発言も伝えられています。
気泡六分儀から高度方位暦に触れさせて頂きました。
ちなみに、大型飛行機での天測の場合、天測窓と呼ばれる窓がコックピットの上の方にあります。所沢の航空公園にあるC-46の展示の機体には天測用の半球ドームがはっきり確認できます。